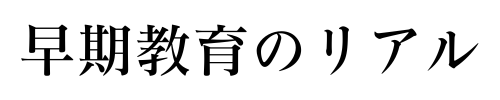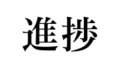今後、子供に国語をどう教えていくか考えていた。放っておけよというツッコミは一旦横に置かせてください。
本当の低学年のうちは、なんとなくドリルを解くことで、新しい語彙を覚えたり、文章を読むことに慣れるという能力が勝手に伸びるから良い。しかし、ある程度文章が読めるようになってからは、正しい方法論がより必要になってくると思う。特に、いわゆる趣味としての読書は好きなようにしてもらえれば良いが、試験としての国語は対策が必要だと思う。
国語の勉強法は間違っていることに気が付きにくい。例えば、算数は違う時には違うとわかる。この違いを説明するときに、自分の脳内イメージとしてあるのは、「王道の勉強法ベクトル」と「我が勉強法ベクトル」の内積。算数の場合は,ベクトル方向が一致するか垂直か、みたいな感じで間違っていることがわかるので途中で修正が効きやすい。だけど、国語はどんな方法でも王道の方法とある程度の相関がある。そして、相関が0.6ぐらいでも突っ走れる気がしてくる。ところが、それでだいぶ長い距離を走って振り返ってみると、王道からとんでもないところに飛ばされている。ここで戻ることができれば良いが、サンクコストの問題もあり、戻りたくない。
おそらく、早期教育をしている家庭の中でも、国語にかける時間がべらぼうに多い家庭は少ない。つまり、他の教科より、学習時間の差には、それほど開きがないと思う。それでも国語の点数は結構開く。さらに、より長い時間軸で見た場合、殆ど全員が頭打ちにあう。それは、例えば、大学受験におけるトップ層において国語を絶対的な武器にしている人が少ないことからもわかると思う。そして、中学受験に無縁であった自分が、大学受験の時に国語で特に困ることはなかったことからも、中学受験の時の勉強が生かされてないような気がする。もちろん、時代の違いもあると思うが。
何が言いたいか。こうした失敗は、今言ったように、国語の勉強の方向が間違っているからなんだと思う。でも、それがほとんどの場合、致命的になっていないということなのだと思う。なぜなら、ほとんどまともに勉強する人がいないから。そして、さらに難しくしているのは、正しい学習を小学校で運よくできたとして。小学校→中学校→高校と同様の方法をブラッシュアップしていく形で勉強するのが難しいこと。中学受験で無双していても大学受験ではそうとも行かない例を見ている。多分、同じ方法論で教えてくれる人がおらず、学習が途絶してしまうからな気がしている。
記号としての数学は比較的どこに行っても同じ。国語も論理的に解くことができれば、中学受験も大学受験も同じ方法論でいけるはずなのに、おそらく色々な先生の、色々な方法論に振り回される。自分もそうであった。
だから、おそらく子供が低学年のうちに、現代文の解き方というものを定着させる必要があるのではないか。そして、それは、かなり責任の伴うこと。先ほど話したように、ずれていたら、それで子供の方法論が固定されていく。ただ単にたくさんのドリルを解かせると、自分流でなんとなくの「点数が取れるかもしれない」方法を見つけ出す。点数が上がらないと、読解力が必要と勘違いした親はさらにドリルを与える。間違った方法での素振りみたいなことが固定され、抜け出せなくなる。悲劇。
一番良いのはプロに教えてもらうことだと思うのだけれど、自分が受験の時を考えても、これで間違いないと言えるようなものには出会えなかった。それは、先生が悪いわけではなく、時間のない中で、方法論を習得するまでの時間を考えると諦めざるを得なかったりという理由も大きい。
そうすると、少なくとも、安心して任せることができる先生に出会うなどするまでは、親がある程度の方向づけをする必要が出てくる。そして、その場合、中学受験の方法論だけで見ていても良くない。その方法論が、大学受験にもつながって、そして一貫して使える必要がある。そんな観点で本屋を彷徨っている。
まだ何も固まっていない。でも、システマチックに解く方法論としては、中野先生の客観的速読法を取り入れるのがありかなという気がする。これを何とか中学受験に取り込めないかと考えていたところ、井上先生が書いた文章読解の鉄則という参考書があることがわかり、購入した。まだ全然早いのだけれど、今後の解説でなるべく無意識のうちに考え方などを獲得させてあげられたらなと思う。
上で責任について書いたけど、子育てをしていると、本当に子供に申し訳なくなることも多い。本人がしたいことは思い切りさせた上で、勉強に関しては、ある意味子供の時間を奪っていることを肝に念じて、将来につながるものにしてあげたい。