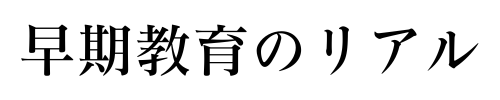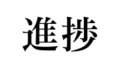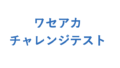長いけど、すごく価値がある動画だと思う。
中学入試と大学入試のそれぞれの国語のプロが、試験問題における類似点と相違点について話し合っている。
全部面白いんだけど、特に、なるほどなと思ったのが、
①37分頃〜
基本的に中学入試だろうが、大学入試であろうが、同じ解き方をする。
違うのは、自分で言い換える必要性とその比重。「わかる」から「表現する」への変換。
これは、全てを自分の力で言い換えなければいけないということではなくて、大学入試だとしても本文の中に使える表現があるのであれば、それは使うべき。
ただし、東大とか京大とかになると、本文の言葉だけではうまく表現できないような絶妙な問題が出される。それが、難しいと言われる一つの原因。そして、そのような問題を中学受験で出す傾向にある学校が筑駒。。
個人的な経験上も納得いくし、中学入試まで獲得しなければいけない能力と、大学入試までに獲得しなければいけない能力がわかる。そして、前回の記事で書いた、なぜ中学入試で上手く行っても大学入試では上手くいかない例があるのかのヒントとなる。
② 小説がなぜ大学入試では出されにくいのか(1:08:38~)
この少し前に二人の食い違いがある。井上先生は小説の解き方として、一般的な常識や予定調和を教えるべき。一方で安達先生は、それでは暗記勝負になってしまう。話をしているうちにその違いが、互いの対象にあることがわかってくる。
中学受験で小説が出やすいのは、小学生が誤読するから。そして、一般常識や予定調和を十分に理解できていないから。本文の理解を問う問題が十分に問題となりうる。
大学受験で小説が出にくいのは、高校生になると誤読が少なくなるから。正解させないためには選択肢を難しくするしかなくなる。つまり、読めてはしまうので、読めたものを表現に移すという段階で難しくする。
つまり、小学生はとんでもない誤読をしうる。一方で高校生はとんでもない誤読をする人はあまり受験に参入をしてこない。この前提の違いが、受験で問われることの違い。
③ 完璧を目指さない。(1:32:00~)
特に優秀層がよく理解しておくべきこと。
プロでも解答がわれる問題は、逆に言えば受験生として間違えても問題ないということ。だから、例えば過去問の答えと学校の正式解答が全く方向性がずれていたら、その問題は受験生としては捨て問で良いはず。確かに!
満点を狙うとガチガチになって6割になる例が結構ある。自然な問題を取りこぼさない8割を狙う。